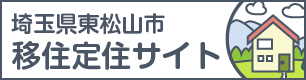本文
古凍祭ばやし
古凍祭ばやし
囃子には江戸時代から演奏されていた古囃子と、明治初期に演奏技術の変革が行われて以降の新囃子とがあります。明治30年(1897年)代は古囃子が盛んでしたがその後中断し、昭和3年(1928年)頃、吉見町の飯島新田地区で伝承されていたものが川島町の下小見野神楽連を経て伝えられ復活しました。明治の頃使われていたと思われる太鼓が残っており、墨書きから「東京浅草区亀岡町」の太鼓商「高橋又左衛門重政」の太鼓であることが分かります。太平洋戦争中は10年ほど中断し、昭和23年(1948年)に復活しました。その後古凍地区だけでなく、正代や松葉町など市内の祭りで演奏し、技術を伝えました。
祭ばやしの演奏
獅子
天狐
オカメ
上演日
4月15日に近い日曜日(お獅子渡御祭・おしっさま)
7月15日に近い日曜日(神輿渡御祭・天王様)
上演場所
鷲神社(古凍499)及び古凍地内
指定年月日
昭和55年(1980年)1月10日(東松山市指定文化財-無形民俗)